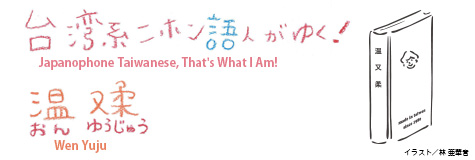
6.『屋根裏の仏さま』を読みました(前篇)
ジュリー・オオツカの『屋根裏の仏さま』(新潮クレスト・ブックス)が店頭に並んだのは今年の3月下旬。刊行直後、たちまち絶賛となりました。
のんきな私は何も知らずに、4月も半ばに入ってから本屋さんで、綺麗というよりは可愛らしい花々が描かれた表紙に惹かれて手にとりました。一枚めくったとたん、もう虜でした。
船でわたしたちはよく考えた。あの人のことを好きになるかしら。愛せるかしら。波止場にいるのを初めて見るとき、写真の人だとわかるかしら。
(『屋根裏の仏さま』より)
『屋根裏の仏さま』の主人公は「わたしたち」。オオツカが「一人称複数形」という一風変わった手法によって
日本人といっても、その出身地はさまざまです。
「繊細で色白で、生まれてからずっと家の奥の薄暗い部屋で過ごしていた」京都の女もいれば、「山口の農家の娘」や「山梨の小さな山村」で育った女、「雪深く寒い北海道」で生まれ育った者もいます。「なんでも見たことがあって、美しい日本語を話」す東京の女たちは、自分たちは他の女とはちがうと思っているのか、「きつい南の訛りでしゃべ」る鹿児島の女たちの日本語を「わからないふり」します。日本の各地から太平洋を渡った女たちはアメリカで出会った沖縄の人のことを「本物の日本人じゃない」とも思っています。
こんなふうに、あらゆる出自と経験と容貌と欲望と不幸と希望を持つ無数の女たちが、『屋根裏の仏さま』を物語る「わたしたち」なのです。
可愛らしい花々が描かれたカバーに惹かれて手にした、日系アメリカ人作家ジュリー・オオツカの新刊『屋根裏の仏さま』(新潮社)。ページを開いたとたん虜になった。
リズミカルな文体を快くたどっていると、無数のシークエンスが、次から次へと浮かんでは消え、また浮かぶ・・・・・・いくつもの短篇映画の予告篇を連続でまのあたりにするときのような心地がします。
私は、とりわけ「子どもら(The Children)」の章に強く惹きつけられました。
ひとつ、またひとつと、わたしたちが教えたかつての言葉は子どもらの頭から消え始めた。子どもらは日本語の花の名前を忘れてしまった。色の名前を忘れてしまった。(中略)子どもらは今では日々新しい言葉で生活している、あの二十六の文字はいまだにわたしたちの頭には入らない。もう何年もアメリカで暮らしているのに。わたしたちが覚えたのはXという文字だけ、銀行で名前のところに書けるようにね。子どもらは、あのlとrをやすやすと発音した。毎週土曜日にお寺へ日本語の勉強に行かせても、ひとつも覚えてこなかった。(中略)でも、あの子らの寝言が聞こえてくるといつも、あの子らの口から出てくる言葉は――ぜったいに確かだ――日本語だった。
(『屋根裏の仏さま』より)
日本語。それは、子どもらの母親――「わたしたち」――のことばなのです。
数年もせずに「lとrをやすやすと発音」するようになる赤ん坊に乳をふくませたり、あやしながら抱しめるとき「わたしたち」は、よしよし、とか、おりこうさん、と囁いたのでしょう。
アメリカという異国で生まれ、育ちつつある子どもらからはmomやmommy と呼ばれているけれど、「わたしたち」が故郷の母親を思うとき心に浮かべるのは、オッカァ、とか、オカアサン、といった響きのはず。
日本語は、「わたしたち」のオカアサンのことばなのです。
アメリカ育ちの子どもらは、かれやかのじょのmomや mommyがそのオカアサンたちから受け継いだ日本的なものを遠ざけます。
子どもらは自分に、わたしたちが選んでやったのではないし、わたしたちには発音もしかねる新しい名前をつけた。ある女の子は自分をドリスと呼んだ。ある女の子は自分をペギーと呼んだ。たくさんの子が、自分をジョージと呼んだ。(中略)エツコは学校の初日に担任の男性教師、スレイター先生から、エスターという名前をもらった。「先生のお母さんの名前なのよ」と彼女は説明した。その言葉にわたしたちは「あんたの名前だってそうよ」と応じた。
(『屋根裏の仏さま』より)
オカアサンのオカアサンの名前を捨ててでも、よりアメリカ人らしい名前を自分につけたがる「わたしたち」の子どもら。
いつしか私はそこに、台湾人の母親を持ちながら日本で育ちつつあった自分自身を重ねていました。ゆうじゅう、という名ではなく、ゆみこ、とか、ゆうこ、とか、もっと日本人らしい名を欲しがっていた時期の。
スミレは自分のことをヴァイオレットと呼んだ。シズコはシュガーだった。マコトはまさしくマック。シゲハル・タカギは九歳のときにバプティスト教会の信者となり、ポールと名前を変えた。
(『屋根裏の仏さま』より)
ヴァイオレットやシュガーやマック、ポールとなった子どもらは、母親の故郷である日本にいる祖母のことばがわかりません。
私とはちがう、と思いました。
オバアチャンのことばが私にはよくわかる。
私の場合、母のことばを忘れることとひきかえに覚えたことばは、オバアチャンのことばだったのです。
台湾人の私の母は、中華民国の国民として中国語を学びましたが、日本統治下の台湾で少女時代を過ごした私の祖母は、中国語ではなく日本語を教わりました。
そのことに思い至り、アメリカで故郷のことばとしての日本語をどうしても忘れられなかった女たちの声と、台湾で宗主国のことばとして日本語を学ばなければならなかった女たちの声とが、胸中でにわかに交錯するのを感じ、眩暈をおぼえます。
以前、日系アメリカ人にとっての日本語や、アメリカに渡った台湾人の中国語や台湾語はどんなふうに表現されているのか想像したくて買った本。『アジア系アメリカ文学 ― 作品とその社会的枠組』『アジア系アメリカ文学を学ぶ人のために』(共に世界思想社)
日系アメリカ人であるジュリー・オオツカは、日本語が母語であるかのじょの祖母や曾祖母の世代の日本の女たちの物語を、かのじょ自身の母語である英語で書きました。そのような物語が日本語に翻訳されて、台湾人だけれど日本語で育った自分が読んでいる。しかも、アメリカに渡った名もなき日本人たちと、日本統治下を生きた台湾人たちを交錯させながら......私にとって『屋根裏の仏さま』を読むことは本当に得難い読書体験でした。
それからほどなくして、一通のメールが舞い込んできます。
――これは夢なの?
思わず目をこすりました。何と、『屋根裏の仏さま』をめぐって、訳者のおひとりである小竹由美子さんと対談して欲しい、というご依頼だったのです。
次の瞬間、私でよければぜひ! と打つ指が震える、というよりも踊っていました。
(後篇に続く)
温又柔 Twitter https://twitter.com/wenyuju




