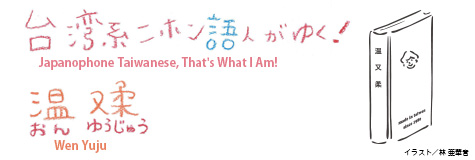
2.わたしは限りなく日本人に近い台湾人です
あれは、高校2年生の春休みのことです。
東京から乗った台北行きの飛行機を降りたあと、空港で預けたスーツケースが出てくるのを待つ間に、わたしはひとりでお手洗いに行きました。用をすませて家族のもとに戻ろうとするのですが、いかんせん方向音痴のため少し迷ってしまいます。うろうろとしていたら、
「日本人ですか?」
声をかけられました。わたしの祖父と同年代と思われる紳士がわたしにむかってほほ笑んでいます。
「お嬢さん、日本人でしょう?」
その方は続けました。大変流ちょうな日本語です。しかしわたしはすぐに、はい、とは言えません。老紳士が質問を変えます。
「あなたは日本から来ましたか?」
そこでようやく、わたしは反応することができました。
「・・・・・・はい」
そのとたん、相手は顔をぱっと輝かせて、
「台湾に、ようこそいらっしゃいました!」
ことばのみならず、顔じゅうでも歓迎の意を示してくれたのです。自分を「日本人」と思い込んでいるであろう老紳士にむかって、わたしは何と言えばいいのかわからず、ほとんど立ち尽くしていました。
折よく、「爸爸、我們走了!(おとうさん、行くわよ!)」という中国語が聞こえました。わたしに声をかけた男性の娘さん、あるいはお嫁さんなのでしょう。わたしの母と同年代と思われる女性に促されてその場を立ち去る紳士に、わたしは会釈します。紳士は最後までわたしに対して親しみのこもった微笑を浮かべていました。
(ようこそいらっしゃいました!)
おじいちゃんも、日本人にむかってそんなふうに声をかけることがあったのかな?
わたしの祖父もまた、あの老紳士のように日本語がとてもじょうずだったのです。祖父だけではありません。祖父の義兄にあたる大伯父もまた、台湾人でありながら日本人顔負けの立派な日本語を話すことができます。
だからわたしは、台湾の老紳士からあのような巧みな日本語で話しかけられたこと自体にはちっとも驚かなかったのです。
やっとのことで、わたしを待ち構えていたようすの両親と妹の姿をみつけて近寄ると、
「もう遅い。何してたの?」
母が私を咎めます。わたしは家族にむかって報告します。
「今ね、日本人ですか、って聞かれちゃった」
父が興味深そうにたずねます。
「そう、それでなんと答えました?」
「はいって・・・・・・」
「えー、おねえちゃん台湾人じゃん」
「ちがうの。日本人ですか? って聞かれたあとに、日本から来たんですか? って聞かれたの。わたしたちは日本から来たんだから、はい、で合ってるの」
妹にそう言い聞かせているわたしに、父が味方します。
「おねえちゃんは正しい。何故なら、君たちは日本人のようなものですから」
父の言うとおりでした。確かに、いつからかわたし(と妹)の表情、しぐさ、相槌の打ち方、佇み方・・・・・・そういった全体的な印象は、台湾人よりは日本人のほうに圧倒的に近いはずなのだから。
そうであるからこそ、あの老紳士からこう声をかけられたのです。
――お嬢さん、日本人でしょう?
ふと「限りなく日本人に近い台湾人」というフレーズが浮かんできます。自分にキャッチフレーズをつけるならコレがぴったりだ、と十七歳のわたしはひそかに得意になりました。

台湾のこどもたちが「ㄅㄆㄇㄈ」と学んでいたとき、日本育ちのわたしはせっせとひらがなとカタカナを練習していた。
――台湾に、ようこそいらっしゃいました!
台湾をおとずれる日本人にむかって、半世紀以上も前に学んだ日本語でそう歓迎する台湾の紳士たちが歩まざるを得なかった人生とはどういうものなのか?
わたしがそのことと真剣にむきあうようになるのは、もう少し先――大学生になってから――のことになります。
 温 又柔(おん ゆうじゅう)
温 又柔(おん ゆうじゅう)
作家。1980年、台北市生まれ。2009年「好去好来歌」ですばる文学賞佳作を受賞。2011年『来福の家』(集英社)を刊行。2013年、ドキュメンタリー映画『異境の中の故郷-作家リービ英雄52年ぶりの台中再訪』(大川景子監督作品)に出演。2014年、音楽家の小島ケイタニーラブと「ponto」を結成し、朗読と演奏による活動「言葉と音の往復書簡」を開始。最新刊は日本で育った一人の「台湾人」として綴った言葉をめぐるエッセイ集『台湾生まれ日本語育ち』(白水社)。この2月に短編小説「被写体の幸福」を『GRANTA JAPAN with 早稲田文学 03』(早川書房) にて発表。
![]()
温又柔 Twitter https://twitter.com/wenyuju


