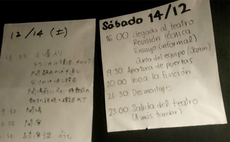海外公演の現場から 岡崎藝術座メキシコ・ペルー公演
2020.6.22
篠原 由香里
(国際交流基金 文化事業部 舞台芸術チーム)
2019年12月、国際交流基金は演劇カンパニー「岡崎藝術座」の中南米ツアーを実施した。カンパニーを主宰する劇作家の神里雄大氏は、大正時代にペルーへ移住した曽祖父母をもち、ペルー・リマに生まれ、移民や越境をテーマにした作品を多く手がけている。2018年には南米体験を基にした作品で第62回岸田國士戯曲賞を受賞した。神里氏の作品は、これまでオーストラリア、ベルギー、フランス、インドネシア等、世界各国で上演を重ねてきたが、中南米での公演は今回が記念すべき初演となった。
上演演目は『+51 アビアシオン, サンボルハ』。若い日本人の演出家が、大正時代、東京で演出家として活躍し、その後メキシコへ亡命し、メキシコ演劇の父とあがめられる佐野碩の亡霊と共に、東京、沖縄、そしてペルーまで旅を共にし、祖母と再会するストーリーである。本ツアーは東京と沖縄での稽古を経て、メキシコとペルーで上演し、リマに住む神里氏の祖母も観劇に訪れるなど、登場人物の足跡をたどるような形で実現した。今回2週間のツアーに同行し、劇場探しや調査などの準備期間を含む約9か月にわたり本事業を担当した立場から、現地での様子や地元の人々からの反響を振り返りたい。

『+51 アビアシオン, サンボルハ』出演の左から捩子(ねじ)ぴじん、福永武史、稲継美保(メキシコシティのベニート・フアレス劇場にて)

独特のせりふ回しや身体表現に注目が集まった(メキシコシティのベニート・フアレス劇場にて)
●メキシコ
メキシコシティは東京から直行便で約14時間。高山病と時差に調子が狂いつつも、本番は3日後に迫っている。チェックが厳しい空港税関で小道具類を全て検査されたので休む間もなく、スタッフ陣はそのまま劇場へ直行。メキシコの劇場スタッフと顔合わせを行い、早速舞台の仕込みを急いだ。
制作スタッフとは半年前からメールでやりとりを続けてきたが、実際現場に入ってから分かることも少なくなく、日本側とメキシコ側の舞台監督、音響、照明と密に話し合い、準備を進めた。メキシコ人スタッフは「問題があればなんでも言ってくれ」と胸を張り、足りないものがあれば舞台監督が自ら買いに走るなど協力的であった。聞けば日本人スタッフとの仕事を楽しみにしていたという。カタカナで名前を書いた養生テープをメキシコ人スタッフに貼ると喜ばれ、列ができた。
一方、神里氏と俳優3名は劇場主催の記者発表へ。日本の現代演劇が披露されるとあり、多くのメディアから熱い視線が注がれた。「日本とメキシコのつながりは何か」「佐野碩の演出方法についてどう思うか」などの質問が浴びせられる中、特に注目を集めたのは神里氏の演劇論、そして俳優たちの意気込みであった。
「ドラマとは、誰かが誰かからメッセージを受けとることで、変化が起きる瞬間に生まれる」と神里氏。「この作品は、日本では遠い記憶となりつつある日系移民について想像をかき立てる意味での"知らせ"として作った。だから俳優がメッセージを届ける先の観客こそが主役だと考える。移住したかった者と、移住できなかった者、双方の視点から、広い意味で"越境"について感じとってもらえれば」。
俳優陣からは、メッセンジャーとして舞台に立つことへの思いが語られた。本ツアーのためにキャスティングされた3名は、出身地も活動拠点もバラバラで、中南米は初訪問。「せりふはスペイン語字幕を通すことになるが、日本語の音や身体の動きなど、観客にメッセージを伝える手段はたくさんあると思う」「ナビゲーターを務める『わたし』と佐野碩の旅物語を皆さんと一緒に楽しみたい」と抱負を語った。
米国と国境を挟むメキシコでは、越境をテーマにした演劇作品が盛んである。迎えた本番には、トラックで越境する移民の悲劇を描いた作品『旅人たちの歌』の演出家、ウゴ・サルセド氏をはじめ、幅広い層の観客が訪れた。
終演後、観客からは「抽象的でありながら、とても複雑で、異文化理解への刺激となった」「とても重要なテーマ。移民は我々全員と関わりがある」といった感想が寄せられた。ウゴ氏も、「メキシコでほとんど知られていない日本の移民にまつわるストーリーは新鮮でとてもよかった。俳優と演出家は非常に優秀で、いくつもの複雑な感情をさりげなく表現していた。クロスボーダー(越境)の概念は、異国間の演劇交流に適している。神里氏の作品をもっと見てみたい」と絶賛してくれた。
結局、会場が閉まる時間まで、多くの観客が客席に残り感想を交わしあっていた。移民問題等、昨今の国際情勢で揺れ動くメキシコの観客に、さまざまなメッセージをもたらしたようである。
●ペルー
メキシコ公演を盛況のうちに終え、また飛行機で約6時間かけてペルーへ移動。同じ中南米とはいえリマはメキシコシティよりも高度が低く、気温は高い。なにより違うのは日本の存在感だ。街中には日本食レストランがあふれ、名刺交換すると名字が日系ということもしばしば。それもそのはず、ペルーは日系人の数が中南米でブラジルに次いで多く、その数は約10万人に達するとも言われている。劇場のペルー人スタッフや取材に来たメディアのインタビュアーの中にも、親戚や恋人が日系人という方が少なからずおり、親しみをもって迎えられた。他方、日本の現代文化へのアクセスは容易ではなく、同時代性の高い現代演劇の上演に興味津々の様子であった。ここでも劇場関係者は皆協力的で、3日後の公演に向けて朝から晩まで準備作業が続いた。
公演に先立ち、そんな日系社会との関係性を象徴する「神内先駆者センター」を訪問した。作中でも登場する同センターは、いわゆるデイケアサービスで、主に日系2世の高齢者が毎日100名以上通っている。まるで日本にいるかのような錯覚に陥るも、飛び交うのはスペイン語とカタコトの日本語、挨拶は会釈にハグとキス、看護師の多くはペルー人。ちぐはぐな視界とは裏腹に、両国の文化は自然に溶け込み、そこに違和感はない。作中で「わたし」が出会う光景そのものを、俳優陣は鋭く観察しながら挨拶をして回った。高齢者たちもまた、はるばるやってきた若い演劇人たち、それも自分たちの先祖を演じる彼らとの触れ合いに、笑顔がこぼれていた。
本番には、地元の演劇好きのほか、神内先駆者センター関係者をはじめ、日本となんらかの接点を持つ観客も来場した。車椅子で訪れた神里氏の祖母もその一人であった。作中、「わたし」がリマの家に暮らし「朝ドラを夕方に見て、夜のど自慢を見る」祖母に会う場面で「おばあ」は言う。「もう一度沖縄に行ってみたいけど、もうだめだよ。年取ったから。もう諦めた」。独特のリズムで発せられるこのせりふに、じっと耳を傾ける観客の姿が印象的であった。一方、「ペルー人運転手の破壊的な運転」や「インカの伝統服を着たホームレス」といったシーンには、客席からくすくすとした笑い声や拍手が上がった。
これらの描写には、ペルー生まれの神里氏ならではの着眼点があり、フィクションでありながら現実とシンクロする説得力もあった。観客からは、「言葉の壁もあり挑戦的な作品だが、彼らの文化を通じてペルーを見ること、また日本の現代演劇に触れる機会は大変新鮮だった」「とても面白かった。日本の俳優による演劇を鑑賞するのは初めてだが、素晴らしい解釈だと思った。彼らの視点から見るペルーが好き」「面白い演出。日本文化や共感について多く学ぶことがあった。もっと知りたいと思った」などの感想が相次いだ。
終演後のアフタートークで、「ペルーとの接点は作品にどう影響しているか」と問われた神里氏は、「自分は日系移民の子孫だが、育ちは日本で、距離がある。だが、この距離感を大切にすることも大事だと思う」と話した。アウトサイダーだからこそ、強いメッセージを発することができるのかもしれない。
劇場の芸術監督は、「日本の現代演劇がペルーで上演されるのは知りうる限り初めてのことであり、大きな快挙だ」と祝福の言葉を送った。ペルー主要紙の『エル・コメルシオ』は、本作を2019年の最も優れた演劇作品の一つに選定した。
神里氏は今回のツアー直後、ペルーでのエピソードを以下のようにつづってくれた。(全文は神里氏note 2019年12月29日付 参照)
ペルー、首都リマ。91歳の祖母が住んでいる。劇中に出てくる神内先駆者センター(デイケア的施設)も、タイトルのサンボルハ地区アビアシオン通りもある。受け入れのスタッフは熱心で、会場はメキシコシティよりコンパクト、なにより標高が下がったこと、湿気の多さに俳優たちの体は変わったようだった。リマではこれまで上演したどことも違う反応が返ってきた。俳優の一人がリマの街の話をし始めると、それまでいぶかしげに見ていた観客も身を乗り出し、笑い、終演後には自分たちの街を外からの視点で見ることで、認識が変化する、みたいな感想を残して帰っていった。
リマの公演のことはいまはまだあんまり書けない。最終日には、神内先駆者センターの人たち、祖母の友人のイサベル(彼女も劇中に登場する)、そして祖母がやってきて客席に座った。
ぼくはこの作品を、私的なエピソードに基づきながらもそれをあくまで素材として見ることで作ることができたと思っていたが、なんだか途中の沖縄のシーンで感極まってしまったのだった。
最前列に座る祖母は、舞台で自分がモチーフとなった話をしているのもわからないようで、けれども神内先駆者センターの人たちは祖母におめでとう、と口々に伝えていて、5年前にこの作品ができたころには、まさかこんなことがあるなんて想像もしなかった。
劇中、「日本のパンはおいしいらしいねと祖母が言うので、今度来るときは持ってきたいのだが難しいだろう」というセリフがあるが、パンどころか作品を持ってきてしまった。祖母からはけっきょく感想を聞くことはできなかったが、5年の時を経てリマの地で言葉にできない感覚にぼくは包まれて、、
そういうわけでセンチメンタルな感じもするし、戸惑いもあるし、とにかくうまく言葉にできないが、この作品は幸せに育った。
この作品をまたやるかはわからない。けれど、作品の評価は高く、リマで新たな仕事が生まれそうな話も出てきて、言葉にできないものをそのままに、今後もぼくたちは作品をつくって上演していろんな土地を回りたい。
ツアー最終日には、現地の芸術監督から神里氏に、ペルーの俳優を起用した共同制作についてのオファーが早速舞い込んだ。神里氏が日本と海外との架け橋を担う気鋭の演出家として、今後ますます国際的な活躍をしていくことが期待される。
国際化とは移動である。人や情報の移動には、起点と終点、内と外といった概念が伴いがちだが、その境界線は極めて曖昧だ。と同時に、境界線を意識することで見えてくるものもある。他国の文化に触れることは、自分を知ることでもあり、その交換は人を豊かにさせる。海外公演はプロセスそのものが国際交流であり、観客や双方のスタッフなど、舞台を囲む全ての人を尊重する気持ちがあって初めて幕が上がる繊細さゆえに、多くの可能性を持っていると感じた。今後も日本と中南米、ひいては世界中との演劇交流が発展することを願ってやまない。
参考文献:『国際演劇年鑑2019 メキシコ:「壁」を越える演劇』吉川恵美子(上智大学外国語学部イスパニア語学科教授)
岡崎藝術座 https://okazaki-art-theatre.com/
2003年、神里雄大の演出作品を上演する団体として結成。
2010年から2012年にかけ、3年連続でフェスティバル/トーキョーに参加。2012年『放屁蟲』(『レッドと黒の膨張する半球体』)で台北アーツフェスティバル(台北)、2016年には『+51 アビアシオン, サンボルハ』でシドニーフェスティバル(オーストラリア)、クンステンフェスティバルデザール(ベルギー)、フェスティバルドートンヌ(フランス)に招聘され、海外公演も多数。2020年7月にはドイツ・ブラウンシュヴァイクの国際舞台芸術祭「フェスティバル・テアターフォルメン」(オンラインで開催)に参加予定。