関連記事
お茶の専門家から文化の専門家へ―家元制度の成立
クリステン・スーラック(ロンドン大学東洋アフリカ学院准教授)
国家元首や国賓をもてなす家元。数百もの弟子が集まる茶会を主催する家元。今日、家元が茶道の流派の頂点に位置することは当然視されていますが、なぜ家元が流派内で絶大な権限を有するようになり、時に政治や国家とも結びつくようになったのでしょうか。そして、なぜ茶道の専門家である家元が日本文化の象徴のように捉えられるようになったのでしょうか。
国際交流基金(ジャパンファウンデーション)は、元日本研究フェローであるクリステン・スーラック氏をお招きし、「お茶の専門家から文化の専門家へ --- 家元制度の成立」と題して、茶道における家元制度の歴史的な成り立ちと変化について10年以上取り組まれてきた研究成果を交えて発表いただきました。
(2014年7月10日 国際交流基金 JFICスペース「けやき」でのセミナーより)
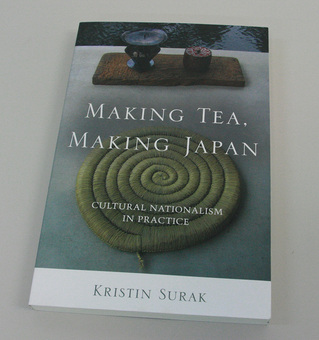
日本の茶道ほどエキゾチックかつ代表的、難解かつ日常的、インストゥルメンタルかつ官能的、政治的かつ文化的な活動はあまりない。日本人の大半は正式な茶会に出席した経験がなく、その難解な手順は多くの人にとって、異質に見える。しかし茶道は、芸術、礼儀作法、そして日本の顕著な特徴とされる感性が、一つの印象的なかたちに統合され、現在も、日本文化を定義する構成要素の1つと認識されている。この茶道がどのような緊迫した状況を通過して現在の姿に至ったかが、この話のテーマだ。
私の研究では一見自然に見える茶道と「日本らしさ」のつながりを紐解いている。つまり、歴史上、どのように確立されたか、茶の世界の組織的構造の中心となった経緯、それが現実として茶道にどのように体現されているか、そして茶人がいかに実際の点前に日本らしさを盛り込んでいるかを分析することだ。今日は、家元制度の役割に焦点を当てている。
 大名茶道と商人茶道
大名茶道と商人茶道
もちろん茶道は、その歴史の大半において、特に「日本的」ではなく、主にエリート男性に代表される活動だった。16世紀後半、日本は驚くべき政治的激変と美学の開花の両方を経験した。織田信長と豊臣秀吉という2人の武将が、支配地域を全国に広げ、統一を進めたのである。これが、翌17世紀に徳川幕府のもとで形成される社会秩序の土台となった。信長と秀吉は、新たに手にした権力を正当化すべく、かつての支配階級・貴族のさまざまな美的慣行を採用した。中でも茶道は、きわめて重要となり、貴族の茶道様式だけでなく、商人の茶道様式も取り入れられた。これは、都市の商人たちの歓心を買う手段でもあった。商人の取り扱う商品、特に軍用品や主要産物、金属は、戦の絶えない天下統一時代において、必要不可欠だったのだ。こうして茶道は重要な政治の道具となった。茶道具は戦の報奨となり、小さな茶会は人脈作りの場として機能し、大きな茶会は軍事的勝利の記念となった。この中で、元商人の茶匠たちは、戦場外の交渉における仲介者として行動した。そうした茶匠の中で最も力を持ったうちの1人が、秀吉の右腕となった千利休である。
利休は、地味な「わび茶」の美学をより洗練させ、新たなレベルに引き上げたが、同時に、派手好みの秀吉の要求にも応じた。この傾向は利休の後任・古田織部にも引き継がれた。織部は、中国起源の装飾的な道具を多用する華麗な「唐好き」の美学を推進し、また、茶室の社会的配置を、社会的境界を乗り越えるためではなく、再定着させるために利用した。これは支配階級の大名にとって好ましい特性だった。秀吉の死後、「大名茶道」と「商人茶道」の分断は決定的となり、政治権力の上部では大名茶道が圧倒的優位になった。
とはいえ、商人茶道も消えたわけではない。利休の死後は孫の千宗旦が、家業として彼のやり方を続け、広めていった。宗旦は利休の名前を(祖父を「茶聖」とすることで)利用して、仲間の茶人や弟子の大きなネットワークを構築した。また宗旦は、当時の他の芸能と同じく家元制度を採用し、自らの地位を制度化した。当時は「家」が、身分制社会の土台として法文化されつつあった時期である。家元は特定の芸能の流派、あるいは様式の長であると同時に、この様式を定義する権威を継承する特定の一族の長でもあった。家元は実質的にこの権利を売り、稽古に金を払う弟子がそれを買う。茶の場合、千家の家元が受け継いだのは、利休の革新的考案や独創的技術だけではない。彼らが定義し、利休に帰した知識体系も受け継いだのだ。利休の遺産を形式化し、点前作法を標準化することで、千家の3つの分派は茶道の多様性を1つの体系にまとめた。彼らはこれを、自らの権威を茶道の主要3領域 ― 点前の技術、道具の価値、味の基準 ― にまで広げることで実現した。
技術について言えば、千家は、点前の手順の正式なカリキュラムを開発することで、専門知識体系を統合して、新たな弟子を引きつけ、その興味を長期間維持するために役立てた。千家は、この課程を形式化し、7段階の技能制度を作った。弟子は免許状を取得することで、利休から伝わるという家元が管理する知識にアクセスできるようになる。茶の点て方だけでなく、道具についても、権威は生成され、拡大された。16世紀にはファウンド・オブジェ(たまたま見つけた日用品) ― 例えば魚を捕るカゴを花器として使う ― を利用する創意工夫が盛んだったが、18世紀には、家元たちは、特定の道具を茶によく合うとして公認するようになっていた。これは文字どおり、道具自体か箱に承認のスタンプを押す(「お墨付きを与える」の意)ことで行われた。また、道具の鑑定も始めた。「血統書」を失った茶碗や茶杓について鑑定書を書き、以前は偉大な茶人の持ち物だったと保証するのだ。そしてついに、彼らは自分たちのスタイルの正典を自らコントロールしはじめた。道具のデザインや制作を自ら手がけることで、権威付けした美意識を促進したのである。
こうして家元たちは18世紀末までに、茶道に対して大きな象徴的な権力を蓄積した。しかし、彼らの影響力には限界があった。遠い地の茶人が中央の指示を守って、彼らの教える商人茶道を実践し続けられるよう、完全に保証するインフラがなかっただけではない。社会の頂点における彼らの存在感は弱く、家元のいない大名茶道のほうが圧倒的に優勢だった。
徳川時代には、茶道の素養は、教養ある男子なら身につけていてしかるべき社会技能だった。しかし1860年代に幕府が倒れると、状況は一変した。明治の日本で茶道が生き残れるかは定かでなく、まして繁栄する保証は皆無だった。千家の家元たちは破産し、諸大名家は解体された。しかし茶道は、権力の行使と深く結びついていたため、切り捨ててしまうことはできなかった。事実、社会の舵取り役を交代した資本家エリートたちは、強欲なエコノミック・アニマルという己のイメージを払拭しようと、それまでの支配者の文化的活動を取り入れた。
こうした実業家たち ― 三井、三越、東武鉄道のトップや多くの政治家など ― は、その市場の活況に拍車をかけただけではない。この頃になると、有名な茶道具は美術品、国宝として再評価されていた。盛大な茶会を開催すれば、権力者が出席し、新聞も大きく取り上げた。家元を持たない彼らの茶道は、新たな担い手を発見したのだ。
一方、商人茶道の当面の見通しは暗かった。明治維新で破産した千家は、新たな絶対的支配者と縁を結ぼうと図り、天皇の良き臣下は全員が儒教的価値観を持つべきだが、茶の修行はそれを養成する手段になる、と主張した。ある家元は、こう宣言した ― 茶の目的は「国家の真髄」を守ることであり、茶は「国家の倫理と礼儀作法の基礎」である。
 家元の生き残りと茶道の女性への広がり
家元の生き残りと茶道の女性への広がり
しかし、家元たちの当面の生き残りにより重要だったのは、別の社会的変化だった。徳川家の支配下では、茶道は男だけのものだった。かつての新封建的秩序の下でも、礼儀作法の一環として茶を習う女性はいた。だが彼女たちは、基本的な点前の薄っぺらな知識を与えられたのみで、正式な茶会で女性が亭主を務めた記録はない。しかし明治政府の下では、女性は窮屈な立場から徐々に解放されただけではない。国の政策にも、その一部 ― 男性よりは下であれ ― であるとして、貢献することを期待されたのだ。1890年代から地方の教育者たちが、多くの女学校で、授業や課外活動に茶道の稽古を取り入れた。
家元たちは、すぐこのトレンドをキャッチし、女学校に茶道具を寄付したり、女学校で授業を行ったりした。明治後期の国家建設の機運の中で、女子の家庭科や修身の教科書は、日本の礼儀作法の独特な長い歴史の一部として、徐々に茶道を強調するようになった。茶は「我が国の女性と過去の国民のあり方の特質」にとって必要不可欠とされ、国家が擁護する理想の「良妻賢母」への指南書として提供された。茶道の国家的イメージは、信長と秀吉による天下統一の輝かしい時代における利休と茶道の話が、多くの歴史教科書に掲載されていたため、さらに普及した。
家元はこの傾向から多大な恩恵を受けた。若い女性は特に大きな収益をもたらす顧客になりやすいからだ。女性には、家元の持つ免状付与の権限が茶道の外の世界でも役立ったから、なおさらだった。家元が発行する免状は、嫁入り道具の1つとして、女性の妻としての価値を公式に保証した(エリート実業家が、このような外部の証明を必要とすることは、まずなかった。彼らにとって、茶道はもっぱら審美的な娯楽だったので)。
しかしもちろん、女性は二級市民であることに変わりはなかった。大起業家たちが高価な茶道具を収集して行う、独自の自由な茶道は名声も高く、家元は大正時代(1912~26年)の終わりまで、そのスケールに対抗できなかった。ところが1928年の金融危機で形勢は逆転。悪徳資本家たちは舞台を去った。彼らが財政的困難と高齢によって落ちぶれたために、軍国主義と国粋主義が色濃くなっていく昭和日本で、うまく立ち回る余地が生じたのである。
1930年代になると、狂信的な愛国主義の台頭で、日本人の特殊性を強調することにますます公的なエネルギーが注がれるようになり、茶道はそのための便利な道具として使われた。たとえば文部省が1937年に発行した『国体の本義』 ― 数百万部が流通し、本土でも植民地でも、学校関係者の必読の書だった ― は、茶道の「わび」の美学を、日本精神の具現の最たるものとして取り上げた。『本義』は、例えばこう説明している ― 「・・・この精神の中で、階級や職業による古来からの差別が覆されて平等な調和が生じ、それによって忘我奉公の精神が養われてきた」。
この雰囲気の中、家元たちが自ら脚光を浴びることになった事態が起きた。1930年代に、秀吉の大茶会と利休の死を記念する2つの茶会が、国を挙げて行われたのだ。これらの巨大イベントには1万人以上が出席。国営ラジオが放送し、新聞でも詳しく報じられた。これによって家元の点前が、茶道の極致として、全国民に披露されたのである。新聞報道では、家元は話に調子を合わせて、こう断言した ―利休[の茶]の中に・・・わびの文化がある、その精神的土台は、日本国民の本質と一致する」。これらのイベントの後に、学者やインテリによる一連のベストセラーが続き、自己犠牲を伴う国粋的軍国主義を大衆に広める手段として、利休の茶を後押しした。
しかし、これは長続きしなかった。1945年、大日本帝国の崩壊と占領軍の駐留によって、家元は、かつて幕府が倒れたときと同じく危うい立場に立たされた。権威主義的秩序の付属物となりはてた伝統的父権社会の信用は失墜し、茶道はその名残として攻撃にさらされたのだ。家元たちは、3世紀近くにわたってかなりの象徴的権力を蓄えてきたが、まだそれを家業に当然伴う属性として確保するには至っていなかった。
 茶道と日本文化の統合
茶道と日本文化の統合
短期間はそうすることができた。自分たちの社会的地位を、2つの相互補完的方向に作り直すことによってである。経済的には、占領終了後のテンポの速い日本式資本主義に同調した、現代企業に変身した。社会的には、文化がナショナリズムの数少ない正当な表現の場だったこの時代に、文化的エリートの地位に上った。敗戦国日本が自らを平和的「文化国家」と再定義するにつれ、家元は自分たち用に新たな役目を考案した。最高レベルの国際交流において、茶道を日本を代表する「日本文化の統合体」として使う、文化大使である(事実、千家の最も有力な一派の当主は、日本の現国連親善大使を務めている)。
このブランドイメージは、さまざまな新事業の売り込みにも役立った。伝統的に家元は、茶道の免状や、稽古や教科書、出版物といった、いわば「茶の専門知識」を売って利益を上げてきた。しかし20世紀中盤以降は経営を多角化。出版社や建築事務所、旅行代理店、短大までも開設し、いまや5億ドル産業になっている。茶の地位が文化の包括的集大成へと上昇するにつれ、家元は茶道だけでなく、日本文化一般についての権威と自認するようになった。日本文化は多くの現代の悪に屈服しつつあると主張し、日本文化の真髄を取り戻す手段として、本やディナー皿、語学講座や客船ツアーを販売するようになったのだ。
典型的なセールストークは、このようなものだ ― 「伝統的な日本の生活様式がすたれつつある」。私たちは「暮らしに対して、誇りを持てる日本的アプローチ」を必要としている。あるいは、「この混乱した社会において、日本の暮らしから品位が失われつつある」治療法は? 「社会をあるべき場所に戻すことができる茶道」。象徴的なエスカレーションと市場拡大が、手に手を取って進んだのである。
家元たちは自らを、日本的洗練の極致として定着させるのに成功した。そのことは、戦後の家元の結婚様式に見て取れる。ある家元は、徳川家の女性と結ばれた ― 幕府の下では考えられなかったことだ。別の家元は天皇のいとこと結婚し、皇室とのつながりに言及するチャンスがあれば滅多に逃さない。これもいい宣伝だが、選挙で選ばれた公職者のトップたちは、必ず家元に敬意を表する。毎年、現首相とお付きの高官らが、新年の最初の週に、東京の千家の一派の本部で、祝いの茶会に出席する。この華やかな催しは、新聞やテレビを通じて国民に伝えられ、茶道における日本の支配者たちの役割が、信長や秀吉の時代から継続していること、そして、そこで主人を務める家元の地位の特異さを見せつけるのだ。
象徴的権力の蓄積から日常的行使への推移を、これほど如実に示す光景もないだろう。
 結論
結論
茶道の日本らしさは、日本のさまざまな意味を凝縮したものとして、家元によって、より重要な意味を盛り込まれ、確保されてきた。第一段階では、家元は本物の茶とは何かを定義し認証する権威を、1人の宗主、つまり家元に投影した。利休につながる系譜を正当性の根拠に、家元はさまざまな革新的な茶の方法を、継承・管理が可能な1つの形式化された知識体系にまとめた。この権威を強化するために、経営管理のメカニズムが発達した。これには細かなカリキュラムや免許制度、および家元の系譜に立脚した権威による、道具の価値や味に対する基準の導入が含まれる。
この間ずっと、茶道は ― 家元の茶ではないが ― 政治権力の頂点と結びついていた。この国家とのつながりが、後年の日本を代表する文化を容易にした。象徴的権力蓄積の第一段階では、家元の主なライバルは武者スタイルの大名茶道だった。大名茶道は徳川、明治、大正時代を通じて、支配階級に好まれる茶道であり続けた。それが変化したのは、近代に大名茶道の担い手となったエリート実業家が1920年代に凋落し、その後、戦争のために文化活動が動員されたためだ。この組み合わせのおかげで家元は、歴史や修身の教科書を通じて広まっていた茶道と日本という国のつながりを我が物にできた。
しかし、日本を「文化の国」としてプロモートする政治的必要性から、家元が茶道のみならず、日本文化一般に対して象徴的権力を行使するようになったのは、戦後になってからのことだ。こうして日本のエリートとしての地位が固まった。家元はその後、茶と日本文化の一体化を利用して、伝統的なベースである茶の知識の範疇を超えた、さまざまな新商品を売り出した。この時点で、第二段階が完了し、象徴的権力が日常的な慣行として行使されるようになった。
茶道は、家元制度の下で権力が集中するという点が多少特異ではあるが、権威の蓄積と行使のメカニズムは広く一般化ができる。経営管理の技術を精緻にしたことで、文化の1分野を構成、統制することが可能になった。活字・放送メディアがその重要性を増幅し、参加者だけでなく社会全体に広めた。エリートの人脈が、象徴的地位を高めるのに役立ち、また、歴史の転機がこうした動きを容易にする場合もある。これらのプロセスは、当事者たちが文化活動である茶道を日本の象徴的地位に押し上げることを可能にし、また、この文化領域そのものを、その国家的意味に物質的投資を行うことによって変貌させている。
クリステン・スーラックKristin Surak
ロンドン大学東洋アフリカ研究学院准教授 。2006年度国際交流基金日本研究フェロー。国際移住、文化、民族、ナショナリズムなどに関する研究は、「European Journal of Sociology」、「International Migration Review」、「Ethnic and Racial Studies」、「Merkur」、「Lettre International」、「New Left Review」などで見られる。著書"Making Tea, Making Japan: Cultural Nationalism in Practice"(Stanford University Press, 2013)は、茶道が日本の象徴としてどのような役割を果たしているかを研究することにより、文化と国家との関係を調べており、アメリカ社会学学会のアジア部門特別出版賞を受賞している。

